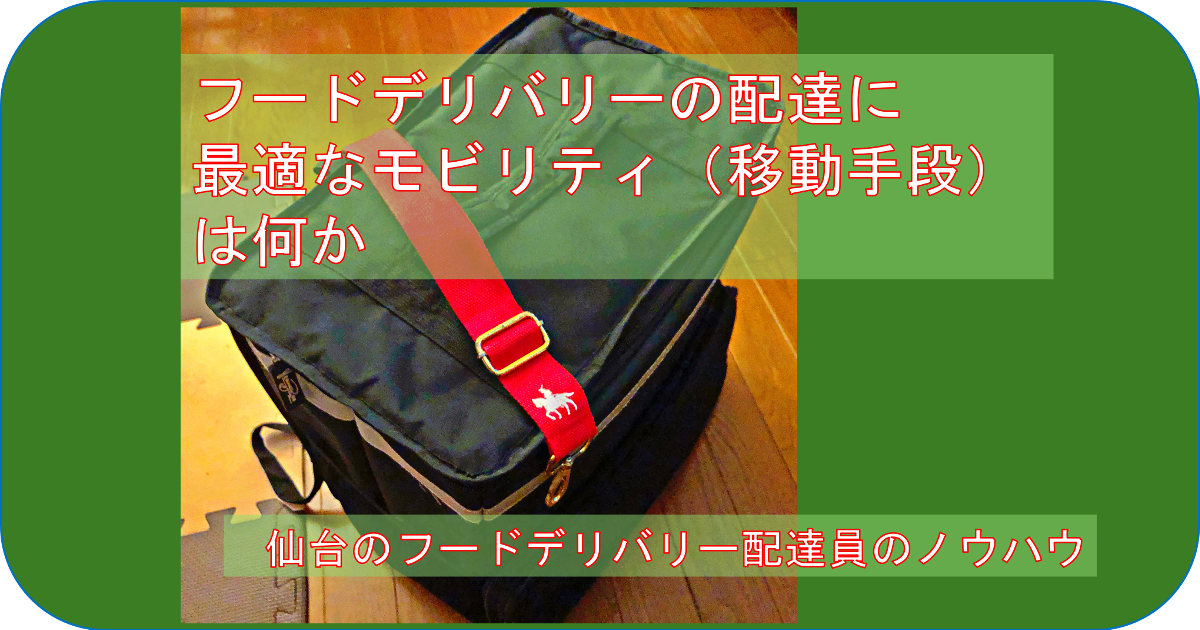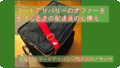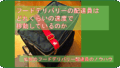世の中にはUber Eats・Wolt・出前館・menu・ピックゴー・Rocket Nowなど様々なフードデリバリーサービスがありますが、全サービス共通で配達員が用意する必要があるものが3つあります。
・スマートフォン(オファーを受けたりピックアップおよびドロップオフの状況を報告したり目的地へのナビを見たりするのに使用)
・デリバリーバッグ(ピックアップした商品を保温・保冷しながら運ぶのに使用)
・モビリティ(ピックアップ地点およびドロップオフ地点に移動するための手段)
今回は上記のモビリティに関する記事です。
おすすめは電動アシスト自転車
フードデリバリーサービスの配達員が使えるモビリティにはバイク・自転車・徒歩などがあります。
その中で私のおすすめは電動アシスト自転車です。
まず徒歩は移動範囲が限られて多くのオファーを獲得するのは難しいと思います。
続いてバイクか自転車かという点です。
稼働する場所の道路事情によって変わると思いますが、私が稼働している仙台では仙台駅周辺に大量の一方通行(自転車を除く)があります。

この「自転車を除く」というのが重要で、バイクはこの道路は一方通行ですが自転車は逆走できます。
移動範囲はバイクの方が広範囲になりますが、この一方通行(自転車を除く)があることで自転車の方がバイクより柔軟な経路を選ぶことができて小回りがきくのです。
また自転車の中でもおすすめは電動アシスト自転車で、フードデリバリーサービスの配達員は同じ坂道を何度も通ったり、一日あたり数時間自転車に乗りっぱなしだったりするので、疲労を軽減するために電動アシスト機能がついている方が良いです。
私が使っているモビリティ
概要

私は2015年に購入した電動アシスト自転車のYAMAHA PAS Brace XLにデリバリーバッグをつけて配達業務に使っています。
バッテリー容量は12.8Ahで、私は毎日6時間程度稼働して2日でバッテリーが切れるので充電しています。
前カゴ

前カゴはYAMAHA PAS Brace XL純正フロントバスケットで、底面積は13cm x 42cmほどです。
前カゴには左から「レインコートを入れた巾着袋」「100円ショップで買った仕切り付きバスケット」を入れ、仕切り付きバスケットの下にはサギサカの超カルフットポンプを入れています。
レインコートは配達業務中にゲリラ豪雨が降っても足止めを食わないよう常備しています。
配達業務をしているとタイヤがパンクしていなくても急激に空気が抜けることがあり、その対策としていつでもタイヤの空気を補充できるようにフットポンプを常備しています。
仕切り付きバスケットには防水ケースに入れたスマートフォン2台(AndroidとiPhone)と、ペットボトルホルダーに入れた水筒を入れています。
防水ケースはLamicallの密閉できるケースで、悪天候の日でもスマートフォンの防水・防塵ができます。
ケースに入れたままスマートフォンのタッチ操作ができますが、ケースに入れていない状態と比べると反応が悪いことがあります。
ケースに付属のネックストラップは邪魔になるので使っていません。
ケースに入れたスマートフォンはA5サイズくらいになるので、ハンズフリーで持ち運ぶ際はA5サイズ以上のポケットが必要です。
水筒は片手ワンプッシュで蓋を開けられるタイガー魔法瓶のMKA-K036を使っています。
配達業務をする上でこまめな水分補給は重要なので、出発時にこの水筒に水を360ml入れて信号での停車時や配達のドロップオフ完了時に水分補給しています。
スマートフォンは、かつては自転車のハンドルにマウントできるスマホホルダーを使っていたこともありましたが、今はカゴに入れるだけです。
配達業務をしているとスマートフォンを自転車から取り出す操作が頻繁に発生します。
ピックアップ地点とドロップオフ地点が各1箇所のシングル案件でも、1日に10個の案件をこなす場合はピックアップ地点でのスマートフォンの取り出しと、ドロップオフ地点でのスマートフォンの取り出しが1回ずつ発生し、合計20回取り出すことになります。
これだけの回数をこなすことになると、スマートフォンをスマホホルダーからはずすことが面倒になります。
フードデリバリーの配達業務では頻繁に発生する作業をいかに効率化するかが重要です。
そのため今は防水ケースに入れたスマートフォンをカゴに入れて、ピックアップ地点とドロップオフ地点ではカゴからスマートフォンを持ち上げるだけ、という運用にしています。
ここで、「移動中に振動でスマートフォンがカゴから飛び出さないのか?」と思う方がいるかもしれませんが、そんな激しい振動が起こるような速さでは移動しておらず、飛び出すことはありません。
またスマホホルダーを使う場合、ホルダーの角度にもよりますが、移動中に配達員アプリのナビ機能を確認する場合にスマートフォンを覗き込む目線と、走行中に見ている目線との角度の差が激しくなります。
前カゴに斜めにスマートフォンを置くようにすると、走行中の目線とあまり変えること無くスマートフォンの画面を確認できます。
後ろの荷台
2025年11月24日以降
2025年11月24日以降、後ろカゴをはずして荷台を拡張するサブキャリアをつけてその上にデリバリーバッグを載せるようにしました。
サブキャリアとデリバリーバッグの詳細をまとめた動画です。
使っているサブキャリアとデリバリーバッグは下記の製品です。
2025年11月23日以前

自転車の後ろカゴはサギサカの縦長リヤカゴを使っています。
底面積は44cm x 24cmほどです。
後ろカゴにはJEJ Astageのラリーコンテナ #15を載せています。
このコンテナはドロップオフ地点でデリバリーバッグから商品を取り出す際にバッグを置く台として使っています。
顧客の住居の玄関までデリバリーバッグとコンテナを持って行き、コンテナを縦にしてデリバリーバッグを乗せて商品を取り出す形です。
自転車のロックはブリヂストンのワイヤーロックを使っています。
鍵は暗い夜間でも差し込みやすい両面ディンプルキーで、鍵の凹凸の向きを気にせずに施錠・解錠できます。
YAMAHA PAS Brace XLは後輪をロックするリング錠が搭載されておらず、またフレームの形状が特殊でリング錠を後付けするのも難しそうなので、ワイヤーロックを使っています。
私が使っているモビリティの利点
・電動アシスト自転車である上に8段変速ができるので、坂道を登る場合でも足と腰の負担が少ないです。
・フラットハンドルなので走行中に肩をいからせるような姿勢をとる必要が無く、肩と腕の負担が少ないです。
・前カゴにスマートフォンを置くことで、スマホホルダーを使わずに複数台のスマートフォンを並べて配置でき、画面の確認がしやすいです。
私が使っているモビリティの問題点
配達業務をする上で最も頻繁に発生する操作はピックアップ地点およびドロップオフ地点への自転車の一時停車なのですが、YAMAHA PAS Brace XLは後輪をロックするリング錠とハンドルロックを実装していないのが問題となります。
停車地点で素早くロックするならばディンプルキー対応のリング錠が最適解だろうと思います。
またハンドルロックが無いと、停車時に地面の傾斜によってハンドルの向きが自然に変わることがあり、その際に勢いよく向きが変わると自転車が転倒することがあります。
自転車のハンドルロックを実現する製品には「くるぴた」がありますが、これはハンドルロック未搭載の自転車に後付けするのは難しいようで、「くるぴた」を標準搭載している自転車本体を選ぶのが良いと思います。
停車中の自転車をさらに安定させるのであれば両脚スタンドもあった方が良さそうです。
ピックアップした商品をデリバリーバッグに詰め込む作業は停車中の自転車の後ろカゴの上でやることが多いですが、片脚スタンドだと詰め込み作業中に安定しないことがあります。
いずれ自転車の買い替えをしたいと考えていますが、その際は「ディンプルキー対応のリング錠」「ハンドルロック」「両脚スタンド」は必須要件にしようと思っています。
今のところ候補に考えているのは上記要件をすべて満たすYAMAHA PAS RINです。